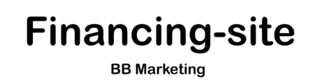【用語解説】手元流動性
← 用語集に戻る
読み方:てもとりゅうどうせい
手元流動性とは、企業がすぐに現金化できる資産(現金、預金、換金性の高い短期有価証券など)の総額を指します。企業の資金繰りの安定性を示す重要な指標であり、突発的な資金需要や予期せぬ支出、あるいは売掛金の回収遅延などが発生した場合に、どれだけ速やかに対応できるかを示すものです。
十分な手元流動性を確保している企業は、資金ショートのリスクが低く、緊急時にも柔軟に対応できます。これは、金融機関からの信用評価にも繋がり、新たな資金調達を行う際にも有利に働くことがあります。
手元流動性が高すぎると、資金が遊んでいる状態となり、本来ならば投資や事業拡大に活用できたはずの機会を逃している(機会費用)と見なされる場合もあります。逆に、手元流動性が不足していると、資金繰りが厳しくなり、最悪の場合には黒字倒産のリスクも生じます。企業は、事業規模や特性、将来の資金ニーズを考慮して、適切な水準の手元流動性を維持することが求められます。